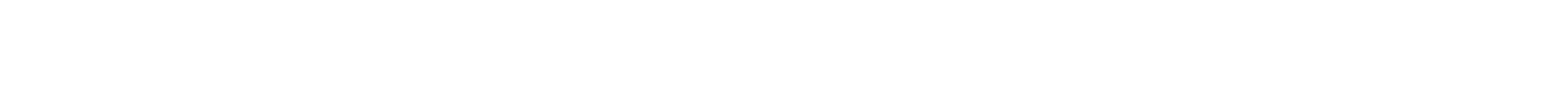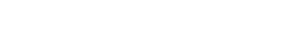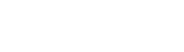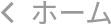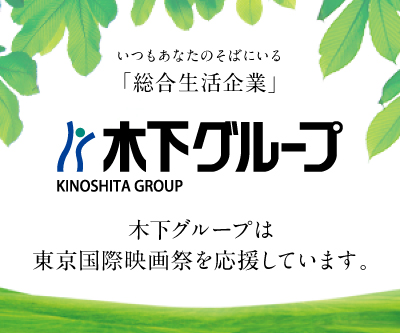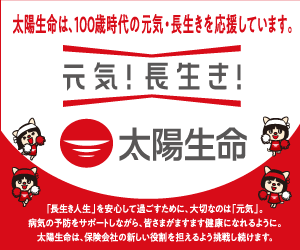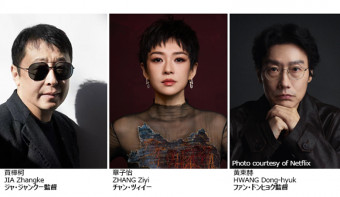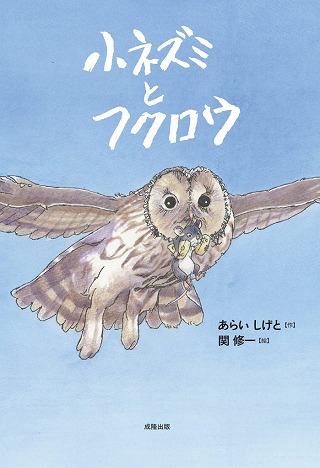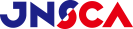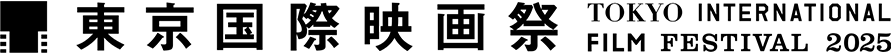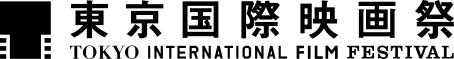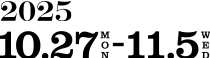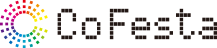古代神話と現代の政治的現実をつなぐ野心的試み コンペティション作『ポンペイのゴーレム』アモス・ギタイ監督インタビュー

アモス・ギタイ監督
巨匠アモス・ギタイ――新作を発表するたび、世界の映画界に新たな衝撃と詩的な問いを投げかけてきた映像作家。その最新作『ポンペイのゴーレム』が、第38回東京国際映画祭コンペティション部門で上映された。この作品はいかに構想され、どのような思想のもとに形づくられたのか。ギタイ監督に、その創造の核心を聞いた。

©AGAV FILMS / Photo by Simon Gosselin
【『ポンペイのゴーレム』あらすじ・概要】
本作は、パフォーマンスのドキュメントとフィクションとを大胆に交錯させ、古代の神話と現代の政治的現実を架橋する野心的な試みである。神秘主義の象徴たる土の人形「ゴーレム」伝説が、滅びの記憶を宿す世界遺産ポンペイの廃墟の中で再演されるとき、そこには単なる舞台記録を超えた、歴史と現在とが交錯する詩的ヴィジョンが立ち上がる。
――なぜ、ゴーレムという主題に取り組もうと思ったのかについて教えてください。
実は1990年代にもゴーレムをテーマに3本映画を作っています。その時、私はパリに住んでいたのですが、その時にゴーレムの大きな役割として私が考えていたのは、コミュニティを守る存在、亡命者のコミュニティを守る存在であることでした。
今も我々は、世界中が大きな政治的な津波に飲まれる大変な状況の中にいます。もちろんその中である範囲では盛り上がりもあって、そこでまた、やはりコミュニティを守る人間の存在が必要だと思ったことが、今回またゴーレムを取り上げた背景にあります。
――本作におけるゴーレムというものについて考えてみた時、まず特徴としてあるのが多言語を使用していることではないでしょうか。
現代の世界は、非常に分断された時代になっている。そうした中で、自分が最近何度も考えていることとして、他者の視点を考えることがあります。現在、イスラエルの人々は10月7日以降、「イスラエルの女性が強姦された」「虐殺された」といったことばかりに声を上げ、それ以外のことを語る余裕を持てない。そしてパレスチナ人もまた、自分たちの街が破壊され、攻撃されたという現実しか見れていないのです。
しかし、人間的な関係というのは、本来、相手側のことも考えなければならないのです。私がたびたび例として挙げているのが、大島渚の『絞死刑』(1969)という映画です。日本の映画作家が韓国人の立場から映画を作っているこの作品のように、映画作家があえて他者の立場に立って映画を作るというのは、とても重要だと思います。
この映画の場合、9つの言語が使われています。それはフランス語、ドイツ語、ロシア語、イディッシュ語、アラビア語、ヘブライ語などで、全部挙げようとすると自分でもどれか忘れてしまうほど多くの言語が使われています。
――とりわけイディッシュ語の使用が興味深く感じました。
イディッシュ語というのは、ディアスポラの言語なんです。つまり、固有の土地を持たない言語であり、しかもそれは迫害を受けた人たちの言語です。主にキリスト教徒からヨーロッパのユダヤ人たちが迫害を受けていた時代に、何世紀にもわたってその迫害に耐え抜く中で使われていた言葉がイディッシュ語でした。本作品で私はその言葉を復活させたいと思ったのです。現代の世界では、キャスティングの在り方が非常に重要だと思っています。この作品でも多国籍のキャスティングを行い、フランス人、イスラエル人、アラビア語を話すアラブ人、さらにイラン人のミュージシャンも参加しています。しかも彼の先祖はロシア人でした。
このことは、現代という時代を象徴する非常に重要な点だと思います。今の世界では、何世紀も何千年も同じ場所に住み続ける、いわば部族的な社会の中にいる人々はほとんどいません。むしろ、世界中の多くの人間は「ディスプレイスメント」、つまり元いた場所から移動させられた人々によって構成されているのです。そして、映画にせよ、文学にせよ、演劇にせよ、音楽にせよ、その現実が反映された作品を作るべきだと思っています。
たとえば、文学を例に出すならばジェームズ・ジョイスの作品がそれにあてはまりますし、村上春樹の文学も、ある意味で自分のオリジンから切り離された言語としての文学であるといえるかもしれません。私は、そうした「起源からの切断」が、現代の芸術において最も重要なことだと思っています。なぜなら、現在のアイデンティティ・ポリティクスの世界では、宗教や国籍、民族など、非常に民族主義的なアイデンティティを人々が強く主張したがる傾向がありますが、現実はそう単純ではありません。
むしろ、本当の意味でのアイデンティティを確立することこそが、大きな力と戦う最大の力になるのだと思います。現代のソーシャルネットワーク、私はむしろ「アンチ・ソーシャル・ネットワーク」と呼びたいのですが、そうしたプラットフォームはマーケティング的な都合によって、人間をグループ分けし、一つのアイデンティティの中に個人を押し込めようとしています。多くの人がそれに従ってしまっていますが、実際のところ、私たちは様々な複数のアイデンティティをまたいで生きているのです。
そのことを皆が自覚することこそが、とても重要なのです。そうすることで、異なるグループ同士の間に橋をかけることができる。自分とは異なる立場の人の感情や思いを考え、理解しようとする――そうした橋を築くことこそが、今の社会の中で、そしてこれからますます重要になっていくことだと思います。
――本作品におけるポンペイの意義について教えてください。
ポンペイはまだ廃墟なんです。そして、それは過去に存在した文明の記念碑でもあります。私は常にストローブ=ユイレの『モーゼとアロン』(1975年、シェーンベルクのオペラをもとにした映画作品)、という映画からインスピレーションを受けてきました。ですから、ポンペイという場所には、歴史や記憶が非常に濃密に詰まっていると感じています。同時に、そこはある種、自然災害によって一瞬にしてすべてが埋もれ、時間が止まったように保存された場所でもあります。つまり、「破壊されながら保存されている」という矛盾を抱えた場所なのです。私はそのような場所に強く興味を持ってきました。
この作品も、たとえば非常にキッチュな現代建築のスタイリッシュな空間で上演することもできたでしょうし、あるいは現代的でありながら半ば廃墟化した集合住宅のような場所で上演することもできたでしょう。そうした空間の違いによって、作品の意味は変わってくると思います。しかし今回は、あえて歴史と記憶が極めて濃厚に刻まれた場所――ポンペイ――で上演しました。
その中で、イレーヌ・ジャコブが非常に素晴らしい演技を見せてくれたと思います。ヴァージニア・ウルフが、この映画の中で引用されている文章を書いたのは、1940年、ロンドンがドイツ軍の空襲を受けていた時期でした。つまり、そのテキスト自体が過去の「破壊の歴史」と深く結びついているのです。
一方で、この舞台の上にあるものは、私たちの現代により近い時代の体験でもあります。私は、そうした現代的な体験を、歴史的な空間の中に置いてみたいと思ったのです。
――本作品は「演劇の上演そのものを映画にする」という、非常に複雑な形式が取られています。映画を監督することと、演劇を演出すること――つまり映画と演劇の違いについて、どのようにお考えでしょうか。
私は大学で建築学を専攻していたので、実は演劇学校や映画学校で一度も講義を受けたことがありません。9年間、建築について真剣に学んだのちに、「そろそろ別のことをやってみよう」と考えたのです。
演劇はそれ自体で尊敬に値する独立したメディウムです。一方で映画もまた、独自のフォルムを持つ尊敬すべき芸術です。異なる芸術形態の規範を他の領域に移行させること――それは非常に興味深い創造的な体験だと考えています。
ただし、現代の演劇を見ていると、しばしば「映画的なイメージを舞台上で再現しよう」とする傾向があります。私は自分が演劇を演出する際には、それは絶対にやらないと決めています。なぜなら、そうしてしまうと、映画と演劇の関係が、あたかも互いを説明するために存在しているような構造になってしまうからです。映画が演劇を説明するためにあるのでもなく、演劇が映画を説明するためにあるのでもありません。
それは映画における音楽の使い方にも通じます。音楽を映像の説明や感情の補強のために使うのではなく、別個の意味を持つ独立した要素として重ね合わせること――そうすることで、新しい解釈の可能性が生まれるのです。映画と演劇を融合させる場合にも、私は同じ考え方で臨んでいます。(取材、文:小城大知/通訳:藤原敏史)
第38回東京国際映画祭は11月5日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。『ポンペイのゴーレム』は、11月2日TOHOシネマズ 日比谷にて18:00~、11月4日TOHOシネマズ 日比谷にて20:40~上映。チケットは公式HPオンラインチケットサイトで発売中。
新着ニュース