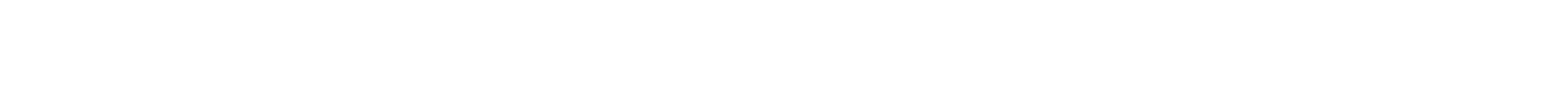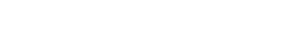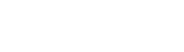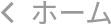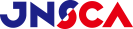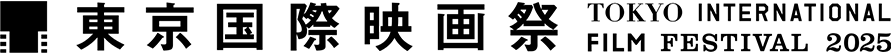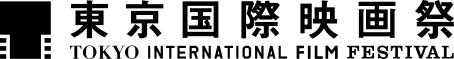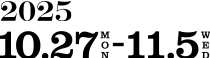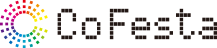10/31(金)コンペティション部門『死のキッチン』上映後に、ペンエーグ・ラッタナルアーンさん(監督/脚本・右)、ベラ・ブンセーンさん(俳優・右から2番目)、クリストファー・ドイルさん(撮影監督・左から2番目)、ダリル・ヨーさん(プロデューサー・左)をお迎えし、Q&Aが行われました。
→ 作品詳細
ペンエーグ・ラッタナルアーン監督(以下、監督):今回、監督と脚本を務めさせていただきました、ペンエーグ・ラッタナルアーンです。本日はご来場いただき、そして、東京国際映画祭にお招きいただきありがとうございます。皆さまからたくさん質問を受けたいので、僕はなるべく長くお話しないようにします。
ベラ・ブンセーンさん(以下、ベラさん):ベラと申します。この映画でサーオ を演じさせていただきました。皆さま、きっと映画をお楽しみいただけたのではないかと願うところです。今回ご一緒させていただき、ありがとうございます。
クリストファー・ドイルさん(以下、クリストファーさん):登壇前に髪の毛をいじられて、髪型が変だったから、この映画のみてくれはさておき、僕のみてくれがOKかどうか、皆さんに確認いただきたいです。(会場笑い)
今回、コンペティション作品に選んでいただいて、光栄に思います。コンペティション作品に選ばれることで、作品が注目を集めるので、非常にありがたいことなんです。
別に良作、駄作というものは無いと思っています。大事なのは、真心と明確な意図を持って、真意で作られた作品であり、アーティフィシャル・インテリジェンス(AI)で作られた作品ではなく、真心で作った作品が大事だと思っています。
今回、ラッタナルアーン監督と組むのは初めてではありません。これからも監督とタッグを組むことが出てくるかなと思います。どういった意図を持って、心を込めて皆さんのために作った映画なのかということが大事だと思っています。
ダリル・ヨーさん(以下、ダリルさん):ダリルと申します。映画にお付き合いくださいまして、ありがとうございます。僕は、ただただこの人たちと壇上に立つことができて、とても嬉しく思っております。皆さまからのご意見やご感想を、とても楽しみにしております。
司会:安田佑子アナウンサー (以下、安田アナ):本当に「怖面白かった」ですよね。ベラさんが(ステージに)登場した途端に、お料理を作ってもらいたいような、もらいたくないような気分になりました。
ベラさんはサーオの15年の復讐心に共感する部分はありますか?
ベラさん:サーオを演じていて、ある種の同情といいますか、共感を感じる部分はありました。15年もかけて男に復讐するわけですが、妙な絆というか、ある種の愛なのではないかと思うんですけれども、そういった感情が芽生えてくるんです。そんな彼女に、少し共感しました。
──Q:キャスティングについて教えてください。
監督:主演のサーオ役のベラさんのキャスティングでは、非常に幸運なことに、オーディションの4、5人目ぐらいの早い段階で来ていただいて。彼女をキャスティングできて、すごくラッキーでした。その前の(出演)作品は、フランス映画とおっしゃったかな。その作品で小さな役を務めた以外は、さほど演技経験がないということで。そんな彼女に4、5人目ぐらいに来ていただいて。そのあと大勢(の役者と)会いましたが、結局、彼女にしようと決めました。そのあと、お茶をご一緒させていただきながら、手の動きや足の動きを観察し、確認しました。
夫役のクリット・シープームセートさんの場合は非常に難しくて。主人公はすぐに見つかったのですが、タイのキャスティング事情はハリウッドと似ていて。女優さんは優秀な方がたくさんいらっしゃるんですが、40代ぐらいで被害者を演じつつも悲愴感を出さない、そういう役を演じることができる人がなかなか見つからない。なぜなら、男性陣はもう少しマッチョですから、そういう難しさがありました。
長いこと見つかりませんでしたが、良いんだか悪いんだか、非常に都合のよいことに、たまたまクリストファー・ドイルさんが結婚されたので撮影を一旦中断しなければならなかったんです。逆に都合が良くて、その待ちの期間を経て、クリットさんをキャスティングして。撮影開始1週間前に決まりました。
クリストファーさん:結婚がコメディなのか、映画がコメディなのかわかりませんけれど。(会場笑い)
監督:劇中で結婚していく彼女も、出演場面は少ないですが、すごく存在感がありました。非常に才能のある方だと思いますので、これから活躍されるんじゃないかなと思います。彼女とビーチに行った若い彼は、コマーシャルに出演していた若手の俳優さんでした。
──Q:どのように演出したのでしょうか。
監督:リハーサル期間は2週間ほどだったのですが、役者が練習するためというよりも、私と役者の協業の中で、キャラクターを掘り下げていく、見つけていく、そういう作業でした。なので、お互いのことをいろいろ学び取りながら作業を進めていったのですが、なるべくそれぞれの性格を自由に出せるような演出をしたいので、役者たちをより深く知るための作業でもありました。演出業というのは、キャスティングとリハーサル、そして編集にもだいぶ助けられるんです。そういう感じです。演出するっていうのは。
──Q:今までに影響を受けた映画監督やこの作品の製作中に影響を受けた映画はありますか。
監督:特にありません(笑)ずいぶん長いこと映画を撮っておりますので、うまくいくこともあれば、いかないこともあるわけなんですが、今回はラッキーでした。
──Q:作品のストーリーはどのように作り上げたのでしょうか。
監督:我々が映画を作る時に、「儲からない」と言われます。なので、今回は「儲かる映画」を(作ろう)と思いました。じゃあ、タイといえば何だろう? タイといえば、食べ物、あるいはマッサージだよね、ということで、目の見えないマッサージ師とシェフとの物語を同時進行で2つ書いていました。先に仕上がった方を撮影しようということで、結局、シェフを主人公にした物語になったんです。次は、マッサージ師を主人公にした映画を撮るつもりです。でも、マッサージ師の脚本は書き上がっていません。結局、妻が夫をどう殺害するのか、そこには至らなかったので。皆さまのアイデアを募ります。是非、お願いします。
安田アナ:映像が本当に美しかったですね。この映像を当たり前だと思っちゃいけないというほど、心の落ち着きを感じる映像、美しさでした。クリストファー・ドイルさんに最後に伺いたいのですが、撮影監督としてのキャリアを重ねてきて、自身の映像哲学で変わった部分はありますか?
クリストファーさん:僕は写真を撮りながら育ったというような家庭環境ではありませんでした。そういう生育環境ではなかったんです。30代の頃の話になりますが、ある方から8mmのカメラをもらい、台湾を旅していろんなところへ行きながら撮影を進めていったんです。写真、あるいはフィルムに詳しい方はご存知だと思いますが、Kodachrome 40 ASA というフィルムで撮影しました。これを現像できるのがオーストラリアの現像所しかなかったので、オーストラリアで現像して、2週間かかったんです。その完成したフィルムを映写しました。その時、エドワード・ヤンさん、ホウ・シャオシェンさんなどの友達と一緒に見たんです。そしたら、真っ黒だったんです。でもそれ(真っ黒だったフィルム)は屋内でのシーンだけだったんです。屋外撮影したそのシーンを映写したら、これがものすごく色あざやかだったんです。緑がすごく緑で、家屋を映してるところはものすごい土色で、空は真っ青で、雲は真っ白でっていう。我ながら見て驚いたんです。つまり、カメラがその被写体にどう反応し、どう捉えるのか、フィルムが映し出された映像にどう反応するかを、当時、僕はいまいちわかってなかったんです。その後、そういったことを学んだわけです。
今でも映画を撮りながら思うのですが、いろんな要素が混ざり合って一つの大きなプロセスになっていくと。どういう顔を映し出していくのか、どういう人々を映すのか、それをどういう素材で撮るのか。それぞれがすべて組み合わさったプロセスになるんです。映画というのは、クエスチョンではなく、答えがあるのみという作業で、間違いもありません。あるのは解像度であったり、パフォーマンスであったり、共に作業をした時間です。そういう感覚で映画を撮っております。いいことを言ったのに、拍手がないな(笑)
(会場笑いと拍手)
安田アナ:素敵なお話でした。皆さんの次の作品も期待しましょう。皆さま、ありがとうございました。