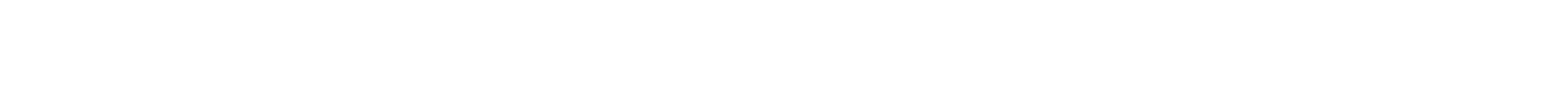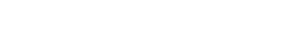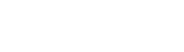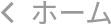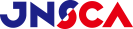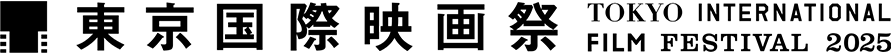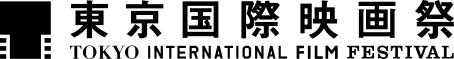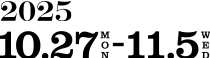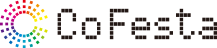11/1のQ&Aに登壇した際のテオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督
11/3(月・祝)、コンペティション部門『マザー』上映後、テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督をお迎えし、Q&Aが行われました。
→ 作品詳細
テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督(以下、監督):東京、大好きです。
──Q:2回目の鑑賞です。劇中、食事シーンが何度かありました。1回目の食事シーンで女性が倒れましたが、これは何を表現しているのでしょう。
監督:2回も観てくださってありがとうございます。たぶんこの映画は2回目の方がいいですよね。
床に横になっていた方ですが、カトリックの中ではよくある光景で、「許しを請う」という所作です。ですので、修道女でああいった姿勢でいることはよくあるんです。横になっている方の隣で、年配の修道女がひざをついています。彼女は逆に、許しを与えて食事を与えていいでしょうかという役割なので、あのような光景が展開しているわけです。
2日前に日本記者の取材を受けた時、その方はボランティアでコルカタで、実際にマザー・テレサと一緒に活動を支援したことがあり、マザー・テレサをご存じだという方にお会いしました。その方が、「私の知っているマザー・テレサはこの映画で描かれた姿に近いです」とおっしゃってくださいました。(映画の中での)彼女の描写は、私の作り物の産物ではありません。長年かけてリサーチをして、様々な証言があります。その状況で彼女がどうだったかということと、彼女が個人的に書き残したものから作り上げられた人物造形になります。彼女の決断力、強さによって、世界を変えることにつながったのです。
──Q:この作品を製作したきっかけを教えてください。女性として、『マザー』を製作する意義も教えてください。
監督:まず第一に、私は女性です。私は常にフラストレーションを感じてきました。歴史上の有名な女性が描かれる時、天使のような、いつも傾聴して誰かに従う(ような姿で描かれる)、もうそれには飽き飽きしていました。
以前、マザー・テレサのドキュメンタリーを手掛けた際、自らリサーチをして、非常に複雑な人物であることが分かりました。私自身、非常に共感する部分が多かったので、彼女の真の姿を描くことが不可欠でした。この映画を作ったことで、私は自分が解放されたし、彼女は、「自分を受け入れる、自分をありのままで自信を持つ」ということ示してくれました。「自分であること」に対して許可を得る必要はないんだと思いました。100年ほど前に生きていた方ですが、生き方には本当にたくさんの学びがありました。
司会:安田佑子アナウンサー (以下、安田アナ):テレサ役をノオミ・ラパス さんに頼みたいと思った理由というのはなんでしょう。2人の間でどんなミーティングがあって、この作品を作り上げられたのでしょうか。
監督:この脚本を書いていて、マザーは反逆児で、ロビン・フッドのように自由を切り開いていく人物なので、深堀りすればするほどパンク・ロックな生き方だなと思いました。キャスティングの段階になって、パンクな感じ→小柄→『ミレニアム ドラゴン・タトゥーの女 』(2010)のノオミさん、という風に繋がったわけです。
1年間かけてキャラクターを彼女と作り上げていくうえで難しかった点は、脆さも出すことでした。強いだけではなく、決断力に伴って常に脆さが同居していることです。それが人間らしさであり、難しい点でした。強さと脆さの緩急を長年かけてノオミさんと一緒に体現しました。
幻覚を見るシーンがありますよね。あれはまさに、テレサの内面の恐れを描いたものです。想像ではありながら、正確に決断に持っていく彼女の強い部分とそれに同居する部分(脆さ)。これを(幻覚を見せることによって)追求したシーンです。ノオミさんって本当に努力家なんです。1年間、一緒に準備をしている間に、朝の5時に「こんなことどうだろう」って電話がかかってきたりしました。
──Q:宗教をテーマの一部として取り扱っているので、センシティブな部分もあると思います。製作過程で気を付けたことがあれば教えてください。
監督:作品のすべてに配慮しました。不可欠ですよね。敬意ももちろん払っています。私は、マインドフル(自分の状況をありのままに受け入れる心の状態)であるということ、キャラクターに敬意を提示するという役ですよね。この美しいキャラクターに素晴らしさを提示する敬意を持ってということだったんですが、もし気に障った方がいたら謝りたいです。
安田アナ:優しい方ですね、ありがとうございます。伝わっています。大丈夫です。それでは、続いていかがですか。
──Q:1946年が舞台になっていますが、装飾等を見るともう少し時代が進んでいるように感じます。
監督:彼女は時代を駆け抜けていった存在です。なので、実は『マザー』では、時の経過を表現しています。バイクに乗った子どもがいましたが、変化を感じつつも何も変わっていない。貧困もそのままで、不平等の状況も変わっていないことをあえて提示しました。(質問者は)すごく観察力がありますね。でも、分かりにくい箇所だと思うので、もう1回観ていただく必要があると思います(笑)。ぜひご覧になってください。
──Q:「サクリファイス(犠牲)」のほうがタイトルに合っているのではないでしょうか。『マザー』というタイトルにした理由をお聞かせください。
監督:女性が主役だと、すぐに「犠牲」と結び付けられることに抵抗があるんです。「自分が自発的に喜んで与えたこと」、それは犠牲ではないと思います。なので、犠牲というタイトルはあり得ません。でも、おっしゃっていることはよく分かります。
私は時間をかけてこの映画を準備するなかで、マザー・テレサが属した神の愛の宣教者会などのことを調べるうちに、謙虚さというものに触れました。今の時代、自己中心的なエゴイスティックな社会になっているなかで、この映画は私たちに警鐘を鳴らすといいますか、思い起こさせてくれます。やはり今、資本主義が頑強で、非常に自己中心的なモンスターがはびこっているなかで、特に必要性を感じます。
このタイトルには、ジレンマもあります。テレサが抱えるジレンマというものが、まさに現れています。つまり、「野心を持った女性」と、「母」「聖人」(のジレンマ)です。
当時、38歳という非常に微妙な年代であった彼女ですが、彼女のことをみんなが「マザー・テレサ」と呼んでいたんです(本名はアグネス・ゴンジャ・ボヤジュ)。ただ、ちょっと、「マザー・テレサ」がタイトルでは不自然かなということも、『マザー』というタイトルに落ち着いた理由です。