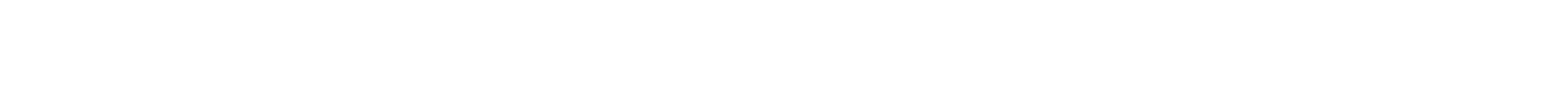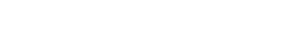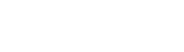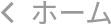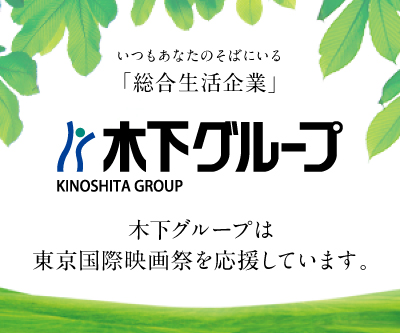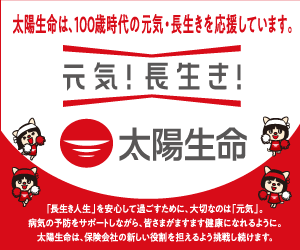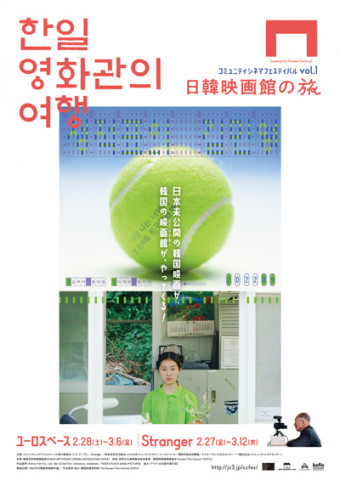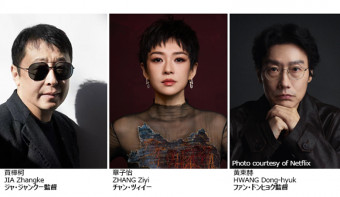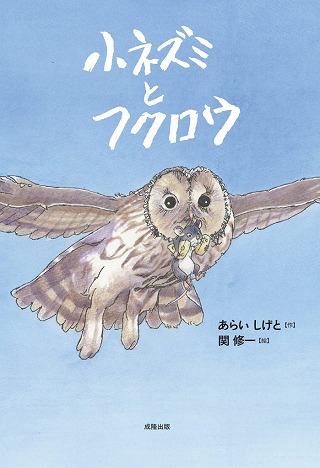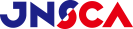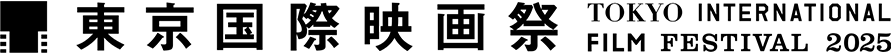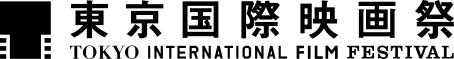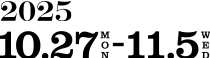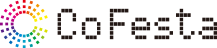消滅の危機に瀕するカンボジアの先住民族に密着 コンペティション作品『私たちは森の果実』インタビュー

© 2025 TIFF
自らの家族をも奪ったクメール・ルージュを一貫した主題として、カンボジアの暴力の歴史と歩みを共にしながら、映画を作り続けてきた孤高のシネアスト、リティ・パンのコンペティション出品作『私たちは森の果実』が上映された。カンボジアの先住民族の一つであるプノン族の生活に、4年の歳月をかけて密着した本作は、いかなる思想のもとに制作されたのか。来日中のパンが、記者たちと「対話」を行った。
【『私たちは森の果実』あらすじ・概要】
カンボジア北東部の人里離れた山岳地帯で、先祖代々の伝統を守った暮らしを続けている先住民プノン族。山の自然と共生する彼らの生活は、国際巨大企業による土地開発と気候変動による深刻な影響を受け、消滅の危機に瀕している。グローバル資本主義が共同体にもたらす弊害、そして文化の「消去」とも言える破壊の過程を描き出している。しかし本作は、単なる資本主義批判にとどまらないより広範な射程を備えた作品として位置づけることができるだろう。
――先住民族の生活とその破壊というテーマを選んだ理由を教えてください。
私はこれまでクメール・ルージュを扱った映画を多く制作してきました。それは私の映画制作の主要な主題であり、私自身の人生の一部でもあります。言うなれば、私の人生の自由そのものであり、私は常にそれと向き合い続けなければならないと思っています。誰かがこの仕事を続けていく必要があるのです。
そして、今回の作品について言えば、私はこれを、クメール・ルージュの時代を知らない新しい世代に向けた、ひとつの「手がかり」や「応答」として位置づけています。もし彼らがその時代について疑問を持たないのであれば、それでも構いません。ただ、もし何か知りたい、理解したいという思いを抱くなら、この映画がその答えや説明の一端になればと願っています。この映画は単に資本主義による部族共同体の破壊について描いているではなく本来、私たちについての映画であり、またあなたについての映画なのです。
――ナレーションにも大きな特徴がありますね。
この映画では、さまざまなものが消えていきます。文化も、伝統も、そして言葉も。その中で「言葉」というのは、とても大きな意味を持っています。私は、彼らに「クメール語で話してください」と言うことはできませんでした。彼らには彼ら自身の言葉があるからです。私はクメール語を理解できませんし、彼らの言葉を完全に理解することも難しい。けれども、だからといって「私のわかる言語で話してほしい」と求めるのは、正しいとは思いません。
なぜ、彼らが私たちの言葉を理解しようと努力しなければならないのでしょうか。なぜ、私たちが彼らの言葉を理解しようと努力しないのか。そこには、明らかにバランスの悪さ、不公平さがあります。私は常に、人々が自分の言葉で歴史を語るあり方を尊重してきました。そこには想像力があり、詩のような美しさがあるからです。
たとえば、スレイマン・シセ(マリの映画作家)と一緒に映画を作ったとき(註:Cinéma de notre temps: Souleymane Cissé (『われらの時代のシネアストたち:スレイマン・シセ』1990)、撮影はバンバラ語で行いました。私はバンバラ語を話せませんが、彼はフランス語で私の言いたいことを理解してくれました。彼に「バンバラ語で言ってみて」と頼むと、何を言っているのか私にはわからないのです。でも、あとでハイチに行って通訳に訳してもらうと、それがとても美しい言葉だったと気づきました。バンバラ語には、響きそのものに詩のような深みがあったのです。
今回も同じです。私は、彼らにできるだけ自由に話してもらいました。そして良い翻訳者とともに、その言葉を後で訳してもらいながら、初めて気づいたのです。彼らの語りがどれほど詩的で、どれほど豊かな描写に満ちていたかということに。
たとえば、ある人が地平線について語ったときのことです。かつてはそこに木々がたくさん生えていたのに、今では何もなく、ただ平らな地平線が広がっている。それを彼はとても悲しんでいました。私たちなら、何もない地平線を見て「自由だ」「気持ちがいい」と感じるかもしれません。けれども彼らにとって、それは「死」を意味するのです。木がなくなり、風や火、土の音が聞こえなくなった地平線──それは、もはや精霊も自然も失われた世界なのです。こうして人々の言葉を聞くうちに、私たちは「見る」ということ、「感じる」ということの意味が、まったく異なるのだと知るのです。
そして、もうひとつ感じたのは、プノン語の構造そのものが円を描いているということです。西洋の言語はピラミッド型です。始まりがあり、展開があり、結論へと向かう。けれども、プノン語の語りはそうではない。井戸のように、円を描くように、何度も同じことを繰り返しながら少しずつ深まっていく。
私はその語りを聞きながら、自分の映像も同じように繰り返すようになりました。西洋の観客には「また同じ映像を見せている」と誤解されるかもしれないと心配していましたが、実際にはそうではありません。繰り返しているようで、決して同じではない。よく聞けば、毎回微妙に違うことを語っているのです。私はその構造をとても好ましく思います。小さな円がいくつも重なり、やがて本質へとたどり着く──その在り方が、とても美しいと思うのです。
そして私は、この映画そのものもそうした構造で作りたいと思いました。もし「これまでの作品と同じように見える」と言われたとしても、それは「はい」でもあり「いいえ」でもあります。もちろん、同じ監督が撮っているのだから、作風や編集のリズムには一貫性があります。しかし、映画というのは常に新しいシネマティック・プロポーザル(映画的に新しい形式を提起すること)でなければならない。私は毎回、映像を通してそうした提起をしたいと思っています。
それが、映画を作ることのもっとも刺激的な部分です。同じテーマ──たとえばクメール・ルージュ──を扱っていても、『S21 クメール・ルージュの虐殺者たち』(2002)と『消えた画 クメール・ルージュの真実』(2013)では、まったく異なる映画的提案がなされているのです。
今回の作品でも、同じようなテーマを追いながらも、そこに流れる言葉、リズム、構造、そして世界の見え方そのものが違う。私は、その違いの中に、プノンの人々と自分を結ぶ何かを感じました。
会場からは、監督の豊かな語りに呼応するように、記者たちから次々と質問が寄せられた。以下に、その質疑応答の内容の一部を紹介する。
――アーカイブ映像の使用について教えてください。
映画によっては数か月で撮影を終えるものもあれば、もっと長い時間をかけて作られるものもあります。数週間で撮れる映画もありますが、私はそうした短い期間の撮影はしません。映画をつくるということは、人々と生活を共にすることだからです。彼らと一緒に暮らし始めると、さまざまな細部が見えてきます。観察する時間があり、精神的なことから料理、食材の集め方に至るまで、さまざまな経験を共有することができます。その意味でも、食はとても重要なものです。
映画に登場する小屋や家には食料の貯蔵場所がまったくありません。それは一種の精神性を示してもいます。彼らは自然の中で、自然と共に生き、必要なものだけを自然から得ているのです。蓄えず、保存もしない──そこには自然への敬意が感じられます。私自身、これまでそのような生活を実際に目にしたことはありませんでした。
あるいは、極度の貧困のためにまったく保存場所がないという場合もあります。しかし、台所で人々と過ごし、共に時間を重ねていけば、日本でもカンボジアでもバングラデシュでもフランスでも、社会的状況や経済的水準、教育のレベルなど、さまざまなことをすぐに理解できるようになります。ただし、それには実際にその場に滞在し、時間をかけることが必要です。
そうしてはじめて、より細やかな部分に焦点を合わせられるようになります。過去のアーカイブ映像というものは、どこか覗き見のようであり、また人類学的な観察の色合いを帯びているのです。
「この人たちは誰なのか」「どのように服を着ているのか」「儀式は何なのか」といった問いが生まれますが、彼らが多くの衣服を身につけることはまれで、その方法を知らないこともあります。だからこそ、そのアーカイブ映像をどのように変換し、どう活かしていくのかを考える必要があるのです。私はアーカイブ映像に反対しているわけではありません。むしろ好きです。ただ、その映像に新たな視点を与え、そこに新しい意味を見いだしたいのです。
それは映像の独立性──つまり映像が本来的に持つ固有の意味の状態ともいえるでしょう。ひとつの映像には、多層的な意味が宿っています。そのうちのひとつを拾い上げ、新たなメッセージを与え、別の映像と組み合わせることで、新しい視点を提示することができるのです。編集の過程では、そうした新しい映像の見方を提案することが可能になります。しかし、それにはやはり時間が必要です。何度も立ち返り、確かめながら進めていかなければなりません。(取材・文/小城大知)
第38回東京国際映画祭は11月5日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区で開催。『私たちは森の果実』は、11月4日ヒューマントラストシネマ有楽町にて18:45~上映。チケットは公式HPオンラインチケットサイトで発売中。
新着ニュース