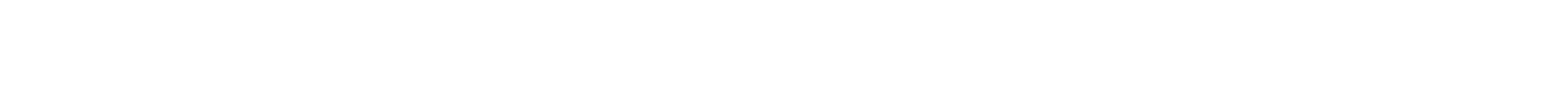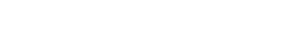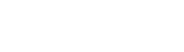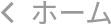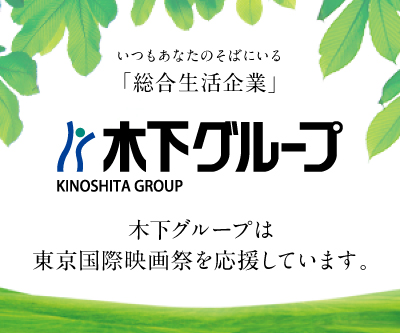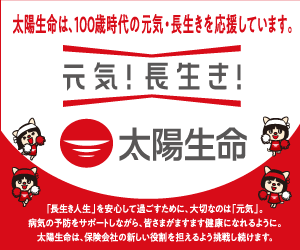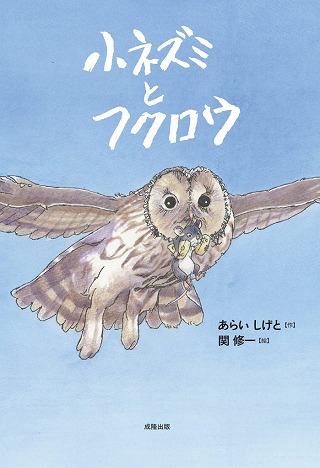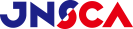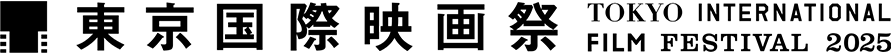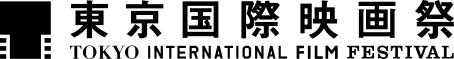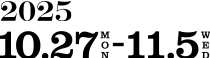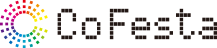10/30(木)、アジアの未来部門『オペレーターNo.23』上映後、シア・ハオ監督をお迎えし、Q&Aが行われました。
→作品詳細
シア・ハオ監督(以下、監督):皆さんこんにちは。劇場に来ていただいてありがとうございます。監督のシア・ハオと申します。東京国際映画祭でお会いできて嬉しく思っております。残念なことに、ハオ・レイ(俳優)さんとシア・ハオラン(俳優) さんはお仕事の関係で来ることができませんでした。皆さんによろしくお伝えください、と言付かっております。
司会:石坂健治シニア・プログラマー(以下、石坂SP):映画の中で、たくさんの西洋絵画の引用が出てきますが、何十枚、何百枚と使われたのでしょうか。先ほどお聞きしたら監督も絵がお好きだと、絵を描かれるっていうふうに伺ったんですけども、美術の世界を作品に描いたことと関係しているのでしょうか。
監督:理由は2つございまして、まず1つ目なんですが、中国では美術大学を受けるのに、西洋絵画で受けなければならないということがあります。ですので、このキャラクターの設定としては、美大生の卵、これから大学を受ける、という設定にいたしました。
2つ目の理由なんですが、キャラクターが思春期の男の子ということで、彼の性の目覚めというようなものを絵画で表現したくて、絵にしました。それから、この映画では絵を視聴言語にして表現しました。皆さんにとっては、もしかしたら新しいかもしれないです。
──Q:時代設定を2008年にした理由をお聞かせください。
監督:理由は3つございます。まず最初は、この映画に登場したようなテレホンサービスっていうのは実は、2008年の中国にはたくさんありました。今回のロケ地にも、そういう場所がありました。でも、当時、僕は若かったので、興味はありましたが入ることはできませんでした。
もう1つは事件ですね。ニュースを聞いたことがありました。そういったポルノチックな電話サービスをしてる組織が警察に摘発されたというニュースです。僕はそこからこの題材を撮ろうと思ったのが1つの理由です。その事件に関わっていた女性はシングルマザーで、普段は小学校の教員だったらしいんですね。もしかしたら彼女はそこで、パートといいますか、テレホンサービスの仕事をしてるっていうのは、お金だけのためではなく、電話を受ける際に自分もどこかで癒されてる部分があるんじゃないかなっていうふうに思い当たって、このストーリーを考えて作品にしようと思いました。
3つ目の理由は、2008年が中国にとってすごく節目な年で、そこから一気に高度成長期に入りまして、国も、暮らしてる人々も大きな変化がありました。そこに焦点を絞って映画を撮ろうと思いました。
──Q:次に挑戦したい監督の作品のテーマは何でしょうか。
監督:今回は少しテーマが重すぎたかなっていう反省をしています。次の作品っていうのは、例えば重いテーマを扱ったとしても少し軽快なやり方で撮りたいなと思っております。
──Qこの映画について、日本の観客の人に伝えたいメッセージがありましたら、よろしくお願いします。
監督:今回のテーマは中国です。同じ日本と同じアジアの国で、やはり親子関係、世代間のコミュニケーションの障壁っていうのはあるかと思うんですが、この時代にあった家庭内の親子関係であったり、社会問題など共通してるところはあると思うんです。日本人の方が劇場に足を運んでいただいて、共感を持っていただけたら幸いです。ありがとうございます。
石坂SP:そうですね。非常に普遍的なテーマということだと思います。
──Q:食事シーンで親子やパートナーの関係性の変化が描かれていたように感じます。どのような意識があったのでしょう。
監督:実は、(食事のシーンは)脚本も撮影も工夫しました。3回くらい食卓のシーンがあります。どうして台所にしたかっていうと、日本もそうだと思いますが、食卓というのは中国人にとってすごく大事な場所で、家族が集まっていろんな家の中の決め事をする場所でもあります。ですので、3回くらい食事のシーンを撮りました。1回目を思い出していただきたいのですが、親子関係がギスギスしていて、あまり会話がなかった状態です。2回目は母親の付き合っていた方が出ていって、それによって男の子は自分はこの家を支えていかなきゃいけないという思いで、彼はすごく大人になって母親の体の具合であったり、関係を改善しようと努力していました。その次の台所のシーンっていうのはかなり、以前のような親密な親子関係に戻ったかと思いきや、すぐにまた大きな事件が起こって、その後ストーリーが続きます。ですので、食卓の3つのシーンはこの映画にとっては流れを左右するような大事なシーンです。
──Q:「23番」という数字は監督にとって何か大きな意味があるのでしょうか。
監督:「23番」っていうのは、先ほど申し上げた事件を聞いた時から頭に浮かんで。「23」を使おうと思いました。なぜかというと、「23」は僕にとって人生の中でいろんな大きな出来事に関わっている数字であって、ラッキーナンバーといってもいいぐらい大事な数字です。
まず電話をかけるには2人必要です。電話をかける人と電話を受ける人、それが「2」という数字です。あと、親子関係。母と子、それも「2」っていう数字になります。「3」というのは、主人公にはそれぞれ大事な人が3人います。母親にとっては息子、付き合っていた方、自殺したテレホンサービスで働いていた方がいて。息子にとっては好きな女の子、母親、23番の電話を受けた方がいます。
そして、「23番」という扉を通して、これからの人生、僕自身の監督としての人生もそうですが、心を大きく開いていろんなものを受け入れるようになりますという思いで、23番にしました。
──Q:私も反抗期の子どもを持つ母親です。この映画の「電話でつながる」ような、何かきっかけがあればいいなと思いました。お母さんが息子を守ったシーンに感動しました。監督は男性ですがどのような気持ちでしたか。
監督:映画に共感してくださいまして、ありがとうございます。そしてご自身の経験もシェアしていただいて感動しております。今の時代、SNSなどいろいろな方法があると思いますので、コミュニケーションが上手く取れるようになる手段はきっと見つかります。頑張ってください。それから、僕が一番いい映画って思うのは、人の心に触れる、触れられるような映画だと思っています。今回お話を聞かせていただいて、観客の心に触れることができ、すごく嬉しく思っています。ありがとうございます。
この映画を撮るにあたって、設定が2008年ということなんですけれども、当時の防空壕の雰囲気が残ってる場所っていうのは少なかったので、コロナ禍でもありロケ地を探すのが大変でした。美術的な観点で2008年の雰囲気を再現しなければならないので、美術の方、カメラマンの方と一緒にロケ地を探したり、素材やいろんなものを探してセットを作ったりしました。この映画を撮る過程っていうのは、僕にとって自分探しの旅でもあったわけです。僕も大変でしたが、このように東京で皆さんに作品を届けることができ、ここで話もできているので、(質問者も)問題は解決できます。頑張ってください。
ハオ・レイさんが演じる母親役の設定は1950年代の方で、実際その時代の女性の方は、日本はどうかわかりませんが、中国の母親はまず子ども第一に考えるでしょう。その時代の方はやはり、実際僕もそうなんですけれども、父親が亡くなっても母親がずっと一人で僕を育ててくれて、周りの友達も見ても、子どもたちを最優先にしています。でも、今の時代の女性には、そうしてほしいとは思いません。大人なので両方選んでいいと思います。
女性に時代が押し付けているような感覚でもあります。現代の女性はそういうことはないと思います。女性は自分の幸せを最優先にしてください。