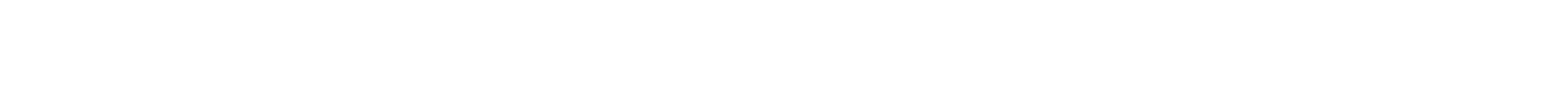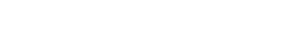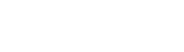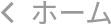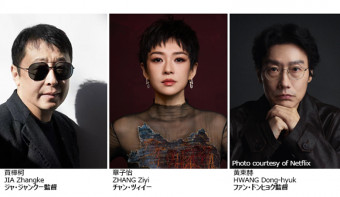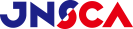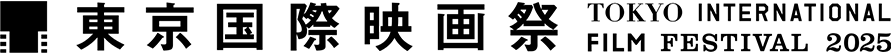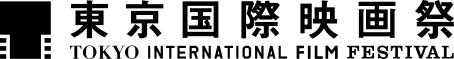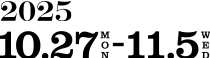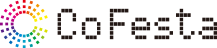日本では『インファナル・アフェア』シリーズ(02-03)の大ヒット以来となる、香港映画ブーム。それに火をつけた『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』(24)。今年ロングラン上映&好成績を記録し、これまで香港映画になじみがなかった若年層にも知名度、人気が波及。アジア映画としても香港映画としても異例のブームを巻き起こした。
そんな“トワウォ”を監督したソイ・チェンが、本編の上映にプラスしてマスタークラスを開催。多忙な撮影中のなか、日帰りで来日し、マスタークラス直前にこのインタビューが実現した。
──マスタークラスでも聞かれると思いますが、まずは“トワウォ”の日本での大ヒットについて振り返っていただけますか?
ソイ・チェン:もちろん嬉しい気持ちでいっぱいですし、正直、今でもびっくりしています。日本の皆さんの反応がこんなに良いものになるとは、想像していなかったんです。振り返ってみると、自分が大人になる成長の過程において、香港では日本文化がすごくいろいろな影響を与えてくれていたことを思い出します。だから、僕達の映画が日本の観客の皆さんに好きだと言っていただけること、また香港映画が好きだって言っていただけることは、非常に嬉しく思うんです。

──80年代の香港映画全盛期から支持している日本の映画ファンはもちろんですが、新しい世代も魅了しています。
ソイ・チェン:そうなんですよね。若い世代──これまで香港映画にそれほど詳しくなかった方々──の非常に良い反応には驚きました。公開後、多くの日本のファンが香港を訪れて、映画のロケ地やセットの展示に来てくださって……いわゆる聖地礼拝っていうヤツですよね(笑)。記念グッズもたくさんを買ってくれてるのは、僕を含む香港の人々も非常に嬉しい気持ちでいっぱいですよ。こんなこと、なかなかないことですもんね。
──日本では、ジャッキー・チェンで育った世代と監督はほぼ同世代。その後、監督がフィルムデビューした90年代は、ウォン・カーウァイなどの全盛期。それらの世代の人達がこれまでずっと日本で香港映画を支持し続けているんですけれども、地元で香港映画を支えている人たちはどんな感じなんでしょうか?
ソイ・チェン:日本とよく似ていると思います。例えば、ウィルソン・イップ監督などの作品群で育った僕よりも若くて新しい世代の人たちも、今おっしゃったような代表的な香港映画を支持しています。観客はもちろん業界人も。映画界を目指す人達はこれら香港映画の代表的な監督の作品を観たことに影響され、業界で訓練を受け、脚本を書いたり助監督を務めたりしています。そうした人たちも、いずれは映画監督になりたいと願っていて、今後、新しい香港映画を担っていく人材として育ってくると思います。
──監督は今回マスタークラスでお越しいただきましたので、すでにマスター。若手の育成については考えていらっしゃいますか?
ソイ・チェン:(笑)。いえいえ。僕はまだ道半ばです。このあとにあるマスタークラスでは、自分自身がどういうふうに監督になったかのか、というキャリアのことや、そのキャリアのなかで問題に直面した時に、監督はどういうことをしなければならないのか。プロデューサーとはどういう協力関係を築くべきか、あるいは、いろんな異なる人たちと仕事をする時にはどういうところを注意しなければならないか……。
つまり、自分自身が監督としてずっと今日までやってきたこと、経験したことをお話ししようと思っています。
もちろん、普段から若い映画人、つまり監督を目指す人たちにも、ある程度こういったお話をする必要がありますね。そうすれば、ある種の心理的な準備ができますから。
──テレビの業界からキャリアを始められ、99年にスクリーンデビューされましたが、その当時はいわゆる香港らしいアクション映画が一番衰退した時期でした。当時の流行は、中国の武侠映画か、『インファナル・アフェア』のようなサスペンス。そんなときから、ずっとノワールやアクションを貫いていらっしゃる原動力はどこにあるんでしょう?
ソイ・チェン:デビュー時はたしかにそうでしたね。不思議に思われるかもしれませんが、当時はすごく使命感みたいなものを持っていたんですよ。
おっしゃるとおり、みんな香港らしいアクション映画から手を引いて、あまり撮らなくなった時代です。香港発祥の振り付けを真似たアクション映画は諸外国でいくつも作られているのに、香港ではなぜ撮らない? もったいないと思わないの? そういう気持ちがすごく強くて。
だから機会があれば、カンフー、あるいはアクション映画を撮りたいと、常に思い続けてきたんです。香港映画からアクション作品が消えてしまうことは、ちょっと想像できませんからね。
──それにしてもすごいタイミングでデビューされたと思います。なにせ、99年は、香港のアクションを基にした『マトリックス』が大ヒットした年。その後、2000年代になると、ジャッキー・チェンとジェット・リーがハリウッドで活躍するようになります。
その一方で本国の香港でどんどんアクション物が衰退していくのは複雑な気分だったでしょう。
ソイ・チェン:本当に複雑でした。(他国では流行ってるのに)アクションをやりたいと言っても、やりにくかったんですよね。
僕はアクション映画を撮る機会に恵まれましたが、実際問題として、アクションができる俳優、そしてスタントマンの問題がありました。なにせ衰退するジャンルだったから、後を継ぐ若い世代が出てこなくて、そのスキルを持った人達はだんだんみんな年取っていくんです。そうなると熟練の技術を持つ年配の役者やスタントマンばかりになってしまう。僕を含む香港の映画人は、この十数年間はある種の分断が起きた時代、と捉えています。なかなかアクション映画が撮れないし、スタントマン、役者の訓練もできなかったので、香港の若者がこの種の作品の作り方を学ぶ機会を失ってしまったんです。
あともう一つ、技術的な問題もありました。アクション映画を撮るときは、いろんなフェイクのセットや美術を作らないといけません。例えば、闘うときに使う棒やナイフ。当時はまだCGがそんなに進んでおらず、擬似的なものをスタッフが作らないといけませんでした。でも、今はそれを作れる人がいない。いくらCGで作れるといっても、技術の継承は出来ていない状況なんです。

──香港映画のなかで、“トワウォ”のように大きいバジェットの作品に危惧されているのは、お話を書ける脚本家がいないことだ、と香港である方を取材した際に伺いました。そうしたクリエイターもまだ足りてないって思われますか。
ソイ・チェン:それだけではありません。例えば、まずアクション映画の俳優たち。今のアクション映画の若い俳優たちは、先ほど言いましたように、20年前のことを全く知りません。20年前のアクション映画に関わっていた俳優もスタントも、高齢であったり、外国で違う仕事をしていたり、あるいは中国大陸のチームと組んで映画を作っています。この新しいジェネレーションの俳優とスタントマンは、イチから全部自分でやらなければならない苦労を抱えています。
同じような状況を脚本家の分野に関しても言えると思うんです。アクション映画の脚本は、脚本を書ける人なら誰でもできる、というわけではないんです。香港のアクション映画は、まずアクションがあって、そのアクションに合わせて物語が展開されるからです。アクションに沿った形で、どういうふうにドラマを付け加えていって面白くするか。これはなかなかできる人が少なく、訓練する場もない。それゆえ多くの脚本家は、アートムービーやテレビドラマに行ってしまうんです。
だから、香港でアクション映画をやる場合は、昔のやり方そのままでは、これからはうまくいきません。新しいやり方も模索しないといけない時代に突入したと思っています。
──監督は過去作で組んだ俳優やスタッフを積極的に継続して作品に起用していますよね。ルイス・クーはもちろん、『西遊記』シリーズ(14-18)で組んだドニー・イェンのチームとサモ・ハンは、“トワウォ”でも活躍されています。
ソイ・チェン:僕にとって、アクション映画での人間関係はものすごい大事だと思うんですよ。アクション映画の主役はだいたい男の子ですし、信頼関係がないと成立しない撮影です。特に“トワウォ”の4人の若手は、映画の撮影を経て本当に親友になりました。これはすごく大切なことだと思います。
──だからか、“トワウォ”だけでなく『ドラゴン×マッハ!/SPL2』(15)や『軍鶏』(07)など、監督の作品からはブロマンスの香りも感じます。意識的に脚本に入れてます?
ソイ・チェン:そうですね(笑)。兄弟の契りや熱血漢といった要素はあったかもしれません。そのなかでも“トワウォ”はちょっと特別かもしれませんね。当初、僕が考えていたのは、観客はみんなルイス・クーやサモ・ハン・キンポーを見たいと思って劇場に来るだろうということ。でも実際は違ってました。若手の俳優たちの関係性をみんなすごく喜んでくださった。これに関しては、僕自身が開眼させられた思いです。
──では最後の質問です。“トワウォ”の続編、続々編に関して言えることは?
ソイ・チェン:それはまだ内緒にしておきますね。期待していてください(笑)。