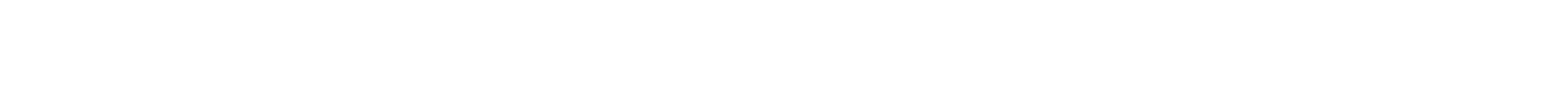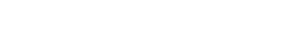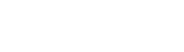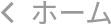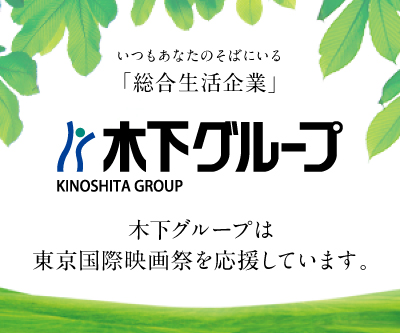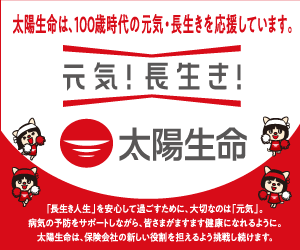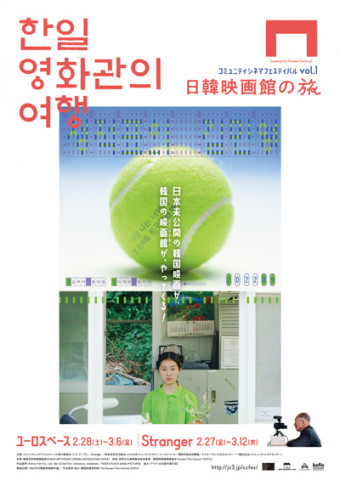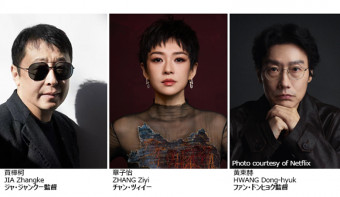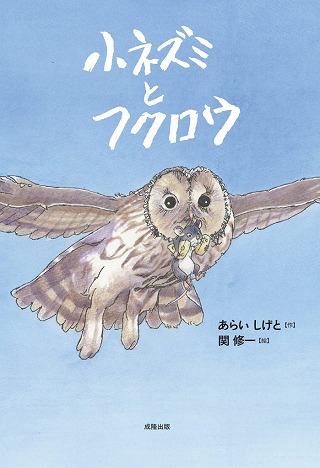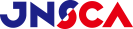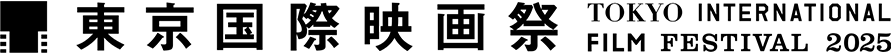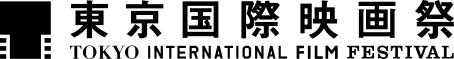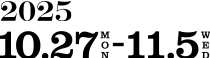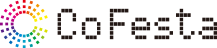東京国際映画祭「アニメーション」部門でプログラミング・アドバイザーを務めていただいている藤津亮太さんが、アヌシー国際アニメーション映画祭のアーティスティック・ディレクター、マルセル・ジャン氏にインタビューしました。2012年からアーティスティック・ディレクターを務めるマルセル・ジャン氏(以下、「MJ」)。氏が現在の“アヌシー”をどう考えているのか聞きました。

© ANNECY FESTIVAL/G. Piel
――2025年のアヌシー国際アニメーション映画祭を終えての感想を教えてください。今年は例年にもまして多くの作品、参加者が集いました。
MJ:一番前向きな手応えは、フィーチャーした作品のクオリティが高かったことです。新しい世代のフィルムメーカーは、ヨーロッパや日本を含め世界中で生まれていて、それが毎年発見されているのが現在の状況です。13年前、私がアーティスティック・ディレクターに就任したときは、まだ世界中で長編アニメーションがそれほど作られておらず、力強いコンペティションを構成するのが非常に大変でした。しかし現在は、本コンペティションとコントルシャン部門と、その両方を成り立たせるだけの十分な数の長編アニメーションが制作され、審査委員にとっても“見せるべき映画”をちゃんと選ぶことができるようになっています。コンペティションに応募する国もアフリカや中南米など世界各地にまで広がりました。これは10年前には考えられないことです。ご存知の通りアヌシーは長らく、短編のコンペティションが中心で、それはとても素晴らしいクオリティの高さでした。しかし、フェスティバルとして成長するためには、様々な意味で露出を高めなくてはなりません。そのためには短編だけでなく長編のコンペティションにも力強いセレクションが必要でした。その点で私たちのフェスティバルはここまでうまく進化してきたと思います。
――問題点についてはどう考えていますか。
MJ:ロジスティックスの問題があります。アヌシーは、東京やパリ、ベルリンのような大都市ではないです。とても小さな町(藤津注:アヌシー市の人口は約12万人)です。そこにたくさんの人が映画祭に訪れるようになったため、ホテルを探すのも、映画祭のチケットを入手するのも、とても大変だと聞くようになりました。来年には「Cite Internationale du Cinema d’Animation」(330席の試写室や展示室、研修施設などを備えた国際研究施設)もスタートするのですが、ホテルに関しては、誰かが新たに開業してくれることを祈るしかない状況です。
――賞について聞かせてください。2019年に長編のコントルシャン部門が新たに設けられ、2023年には長編本コンペティションの中にポール・グリモー賞が設けられたりと、近年映画祭の中で賞が増える傾向にあると感じられます。
MJ:私たちはここ数年の間、部門の新設を含めて、なんらかの変更を加えてきました。それは世界各国のアニメーション制作の現実を見て、それを反映しようとしているからです。私たちのフェスティバルは世界で一番大きなフェスティバルです。そして『スパイダーマン』でもいわれているとおり、大きくなればなるほど、責任も大きくなるわけです。世界でこれまで以上に様々なアニメーションが制作されています。そこでなにが起きているのかをちゃんと映画祭で見せないといけないと考えているからです。
――世界のアニメーションの現状に応える形で映画祭も変化しなくてはならないと。
MJ:そうです。コントルシャン部門を作ったことがいちばんわかりやすいと思います。私は映画というのは、その内容にあったところで見てもらうべきだと思います。そう考えたとき、実験的な映画を本コンペティションと同じ大きなスクリーンで見てもらうのは得策とはいえない。もしそうしたら、観客にネガティブな受け止められ方をしてしまうかもしれない。だから例えば山村浩二監督の『幾多の北』というのは、コントルシャン部門で見てもらうのがもっともふさわしいと思ったわけです。そしてその結果として(2022年の)クリスタル賞の受賞にも納得してもらえると思うわけです。これは短編も同様です。
――つまりどんなスタイルの作品ができても、それにふさわしい回路を開けるようにしている、と。
MJ:おっしゃるとおりです。今年は折笠良監督が『落書』で受賞した短編のOff-Limits賞も同様です。Off-Limits賞を設けたのは実験的な短編アニメーションを、より見やすくしたいと考えたからです。近年、短編は1本あたりの上映時間が長くなっています。昔は8分から9分ぐらいのものが中心でしたが、今は15分を超えるものも多くあります。これも短編の見せ方が変わってきた理由のひとつです。一方で映画祭にジャンル映画を求める人も増えています。そこでフェスティバルの中でそういう映画も見られる機会を作りたいと思い、ミッドナイト・スペシャルという部門も設けるようにしました。
――映画祭が多彩な作品を扱うようになった結果。本コンペティションの存在感が弱まってしまうような心配はありませんか?
MJ:今の時点では、そういう懸念は持っていません。例えば本コンペティションに選ばれた作品のチケットは、発売開始5分で売り切れてしまうこともあります。マスコミも映画祭に参加している方も、一番の関心はやはり本コンペであることに変わりはありません。ほかの部門のコンペティションもいいんですけど、やはり本コンペのテンションは特別なものがあるのです。
――審査を行う上で、審査委員間で共有されているポリシーのようなものはありますか?
MJ:基本的に、審査委員にすべてを任せ、自由に決めてもらうようにしています。「任せる」ということはとても大事だと考えています。その上で、コンペティションに入れる作品を選考するにあたっては「どの作品がなんらかの賞をとったとき、自分がそこにプライドを感じられる作品を選んでください」とお願いしています。またコンペティションの審査にあたって毎年私が言っているのは「自分自身の中でなにか繋がるものがある作品を選んでください」ということです。もちろん意見が分かれて、ディスカッションすることになる場合もあるでしょう。でも、その時も全員が「これだ」と思えるものを決めるまで説得しあってほしいです。コンペティションには、時に物議を醸しそうな要素のある映画が入ってくることもあります。それについても細かいことはいわず「映画祭のプライドになるような作品を選んでください」とお願いしています。
――ありがとうございました。
アヌシー国際アニメーション映画祭
⇒ 公式ウェブサイト annecyfestival.com (英語ページ)