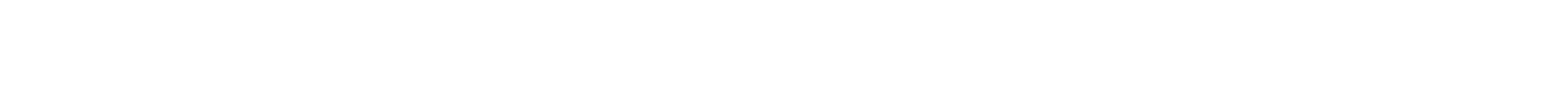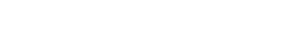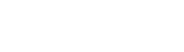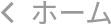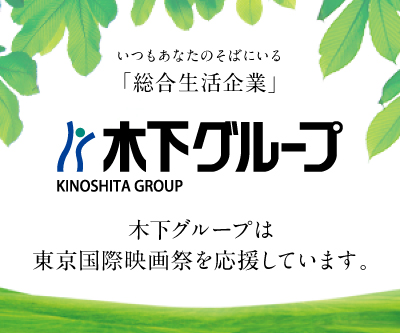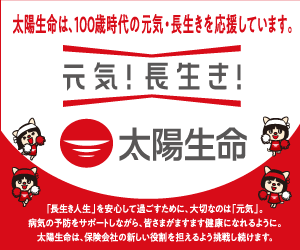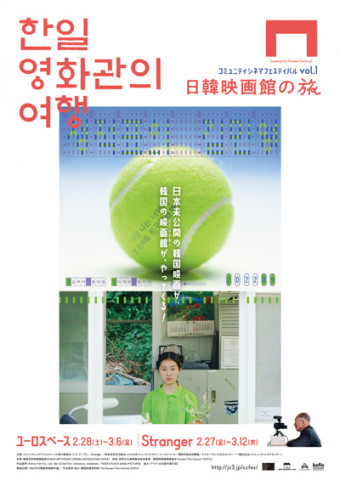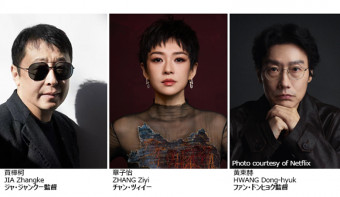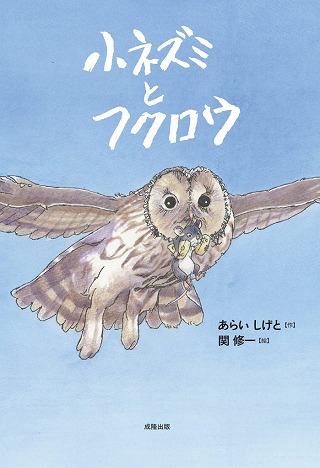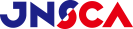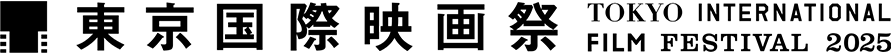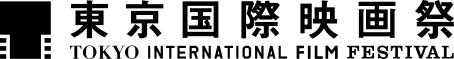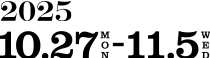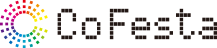10/28(火)、アジアの未来部門『黄色い子』上映後に、今井ミカさん(左から2番目:監督/脚本/編集)、今井彰人さん(右:俳優)、人夢さん(右から2番目:俳優)、グー・ユーシャンさん(左:俳優)をお迎えし、舞台挨拶/Q&Aが行われました。
→作品詳細
司会: 石坂健治シニア・プログラマー(以下、石坂SP):今日はできるだけバリアフリーで、皆さんにお届けしたいと思っております。いつもとパターンが違いますが、穏やかに、楽しく進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
司会は私、石坂です。私の隣に手話通訳さんがいらっしゃいます。そして、最前列に英語通訳の方、日本手話通訳の方が2人いらっしゃって、台湾手話通訳の方がお一人いらっしゃいます。舞台挨拶ということで、まずは今井監督お願いします。
今井ミカ監督(以下、監督):皆さん改めまして、今井ミカと申します。監督を務めました。本日この場で上映できたことに大変喜びを感じています。また、ろう者、聴者、海外の方々、たくさんの人々に観ていただけたこと、本当に改めて感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。
グー・ユーシャンさん(以下、グーさん):グー・ユーシャンと申します。本日、台湾から参りました。今井監督と出会い、話を進めて親しくなり、主演を仰せつかることになりました。今回、『黄色い子』というタイトルにもかかわらず、私のような年配者が主演です。台湾と日本で手話は異なりますが、日本手話の約60%が台湾手話に似ているということもありまして、コミュニケーションはスムーズに取ることができました。監督が映画の撮影で台湾に来てくださいましたが、日本の映画監督としてすごく有名な方だと後で知ってびっくりしました。これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
人夢さん:人夢と申します。黄色い子のみつきを演じました。今日はたくさんの人に観ていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございました。
今井彰人さん(以下、今井さん):私、今井彰人と申します。よろしくお願いいたします。父親役を演じました。昨年から父親役を演じる機会が多く、そろそろもう、年相応でしょうか。35歳なのですが、父親顔ということでしょうか。少し複雑な気持ちになっております(笑)。今回の父親役は、今までに経験のないチャレンジの役でした。このような作品に出演することができて嬉しく思います。そして皆さん、たくさんの人で、満席で、お越しいただきまして嬉しく思います。今日はいろいろお話できればと思います。ありがとうございます。
──Q:日本人のろうの迷子の子どもを探すシーンで、警察などの公的機関ではなく、ろうの社会だけで解決しようとしていました。台湾の社会性、ろうの社会性が関係しているのでしょうか。
監督:ご質問いただきましてありがとうございます。ろうとして育っているという設定、つまりは第一言語が日本手話という設定です。ですので、日本語はあくまでも第二言語です。日本語と日本手話は別の言語ですので、主役の子は、日本手話が第一言語という設定です。
さらに現地は台湾ですので、まったくの異国を訪れて、そこでろう者であるという立場、しかも迷子になっているという状況です。どのようにコミュニケーションをとるのかというところに大変な不安を感じると思います。聴者であれば、音声を使えますし、台湾であれば日本語が話せる方もいないわけではありません。けれども、日本手話になるとどうなりますか?台湾の聞こえる人が果たして日本手話ができるのか、というところがありまして、色々と検討し、社会を変えていく必要もある。つまり、手話に対して「言語」であるという理解を広めていく必要があると思い、このような内容にしました。
──Q:監督に質問です。ドキュメンタリーを見ているような演技や、視線の細かい演出が印象的です。役者本人がどのように感じるのかを引き出すようにして撮影したのでしょうか。
監督:ご質問いただきありがとうございます。ご質問いただいた通りなのですが、会話を重ねて本人の気持ちを引き出す時間をかなりかけました。物語を手話で、動画で撮影したものがあるのですが、現場の状況にそれが合わなかったり、あるいは、現場の雰囲気であったり、その場で起きた気持ちに合わせて物語も適宜修正しています。
例えばですが、おじいさんと黄色い子が抱き合って、警察に行きたくないと泣き叫ぶシーンがありましたが、その場で話し合いました。すごく大変な思いをしたのですが、「もし1人で台湾で本当に迷子になって警察に行きなさいって言われたらどうする?」というように人夢に問いかけて。それで、「何で怖いの?」と言ったらやっぱり言語が違うから、通じないと考えると想像できない、怖いって言ったんですね。このような形で、実際に現場で「こうだったらどうする?」というような会話を重ねて、うまくその状況に踏み込んで、彼自身の気持ちを引き出して撮りました。想像しながら演技をしてもらったというところです。
石坂SP:人夢君、撮影は楽しかったですか?それとも、難しかったですか?
人夢さん:少し難しかったです。特に泣くお芝居の時に最初はなかなか涙が出なかったんです。コツとして2つあります。練習をしたことと、もう一つは、想像力を働かせました。何を想像したかは内緒ですけど、色々想像しながらお芝居をしました。(会場笑い)
──Q:台湾手話と日本手話でコミュニケーションをとるのは大変だったと思います。お芝居をしている中で、すれ違う部分や大変だったという話があればお聞きしたいです。
グーさん:第二次世界大戦の日本との歴史的な背景もありまして、台湾に日本の手話を教えていたという歴史があります。私のような70歳以上の高齢者であれば、手話の60%が日本手話の影響を受けているということになります。
今の若い人たちが使っている手話も40%ぐらいが似ているということで、今は少しずつ日本手話の影響は少なくなっていますが、人夢と会ってコミュニケーションを取ることによって、日本手話を使えていた時代を思い出しつつ、コミュニケーション自体はうまく取れていたと思います。
ろう者の中で多いのは、日本から台湾に行ってろう者と交流する、逆に台湾からも日本に行って交流することが増えています。ですので、台湾手話と日本手話は似ていて、例えば、父、母、兄、弟というようなものは、日本手話と台湾手話は同じものが使われています。
石坂SP:ありがとうございます。手話をとってもアジアの歴史が見えてくるということだと思います。
──Q:映画のストーリーのように、ろうの子どもが迷子になってしまった場合、社会にどのようなサポートを求めますか。
監督:もしこのようなことが起きたら、警察に連絡をする必要は当然あると思いますが、それだけでは足りません。やはり、ろう者協会ですね。ろう者協会は世界中にほとんどありますので、ネットで調べてろう者協会に相談をしていただきたいです。そうすると、協会にろう者がいて、すぐにサポートに入ってくれ、一緒に行動することができます。やはり、聴者だけでは解決が難しいので、警察に連絡するとともに、ろう者協会にもご連絡いただけると大変ありがたいです。
石坂SP:ありがとうございました。この後写真撮影に移りますけれども、その前に最後の挨拶を一言ということで、今井彰人さん、最後に一言この場を締めていただくということでいかがでしょうか。
今井さん:この作品がみんなにとっての第一歩という風に感じています。個人としては少しずつ、みんなと一緒に亀の歩みで頑張っていきたいなと考えておりますので、どうぞ皆さん、応援をよろしくお願いします。こんな感じで締めになりましたでしょうか。
石坂SP:監督、何か言い添えることはございますか?
監督:はい、一つありまして、ろう者が見れば分かると思いますが、この映画の中には、方言といいますか…「東京の手話」、「群馬の手話」、「日本の手話」、「台湾の手話」もそうですし、様々な手話の違いというものが映画の中に込められていますので、本当にいろいろな言語が入り混じっている作品に挑戦しました。聞こえる聴者の皆さんが見ると、ちょっと分かりづらいのかもしれませんが、何度も(映画を)観て、あるいはろう者に聞いて、深みを込めて見ていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。