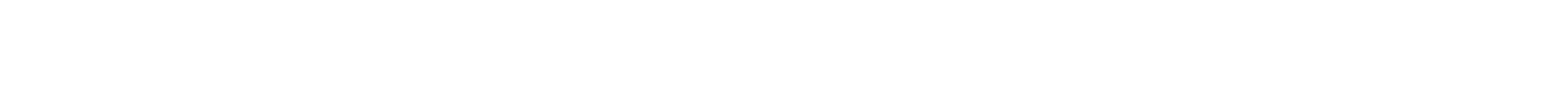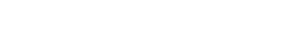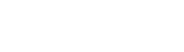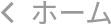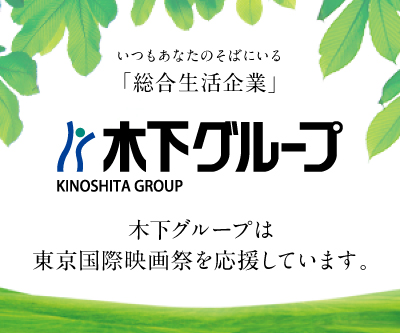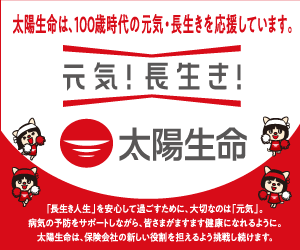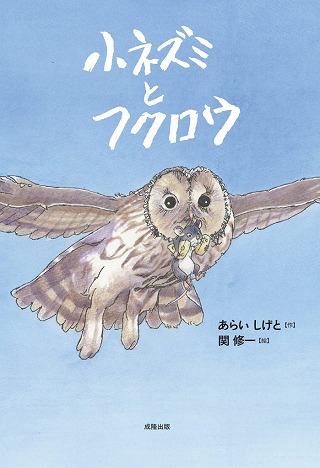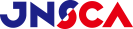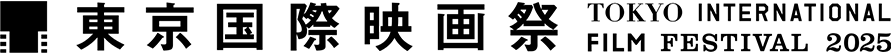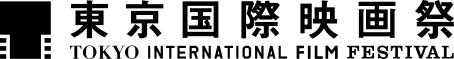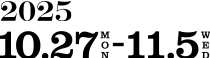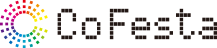東京国際映画祭公式インタビュー 2025年10月30日
アジアの未来
『オペレーターNo.23』
シア・ハオ(監督/脚本)

父が行方不明となり、ときが経つにつれ母との関係は悪化する一方の、美術を専攻するハン・イエ。彼は偶然拾ったテレホンクラブの番号に電話をし、オペレーター23番との会話に安らぎを求めるように…。こじれた母子関係とやり場のない孤独に苦悩する青年が、テレホンクラブのオペレーターとの会話で少しずつ解放されていくさまを描くヒューマンドラマ『オペレーターNo.23』。この作品で長編監督デビューを果たしたシア・ハオに、デビュー作のモチーフ、思いを聞いた。
──アクション映画の助監督からこういったヒューマンドラマ、アートハウス系の映画で長編監督デビューされました。デビュー作にこのジャンルを選んだ理由は?
シア・ハオ監督(以下、シア監督):この作品のアイデアは2008年からあったんですよ。アイデアだけでしたが、これを長編にすることは長年の夢だったんです。夢がかなった今、次からはいろんなジャンルのものにチャレンジしたいなと思っています。
──本作は、2015年にカンヌ映画祭マーケットで行われたNew Chinese Film Talents Fund Forumで最高賞を獲得、支援を受けていますね。その時の脚本から今回の完成したバージョンの脚本に至るまではかなり時間がかかってますが、プロットの大きな変更はどこになりますか?
シア監督:ハン・イエがオペレーターと電話しているときにインサートしている絵画のパートは、後から生まれたアイデアです。あのシーンは、主人公ハン・イエが思春期の男の子なので、男の子の心の揺れ動き、“性への目覚め”を表現するために考えました。

──カンヌで提出したプロットから「23」という数字が使われていましたが、この数字にはどういう意味を持たせているんですか?
シア監督:観客からも質問があったんですけど、自分の人生の中の要所要所、大事な時期には「23」が関わっていたんです。また、ばらしてみると、「2」は親子、母と子。それから、電話を掛ける人と受ける人。「3」は、息子と母親それぞれに大事な人が3人いること。息子には母親と好きな女の子、それに23番のオペレーターがいる。母親は息子と彼氏、それに同僚のメイさんがいて3人。2008年にある事件のニュースを見てこれを撮ろうと思ったんですが、後になって考えてみると、その年は僕がちょうど23歳になった年だったんです。
──運命の数字ですね。監督は美術を専攻されていらっしゃいましたが、あの絵画のインサートのアイデアはどこから? また本物を写した写真を使っているんですか?
シア監督:編集時に作りましたが、当初は順番を考えていなかったんです。編集のときに、徐々に西洋絵画の本の中の順番どおりにインサートしていくことにしました。また、最初は画面いっぱいに絵画を出さず、ちょっとインサートし、最後に大きくして画面いっぱいに。オペレーターとの会話で妄想を膨らませ、現実に戻るまでの心の中の動きを表現するために、このような工夫をしました。
──あのアイデアの発想源は?
シア監督:ハン・イエは美術専攻の学生なので、名画はどこかで使おうと思っていたんですが、編集するときに取っておきました。というのも、(名画をキャラクターの心情を描くためにメタファーとして使った)似たような感じの映画は見たことがあるんですけど、絵画を動画みたいに加工して使っているものが多かったんですよね。それでどこまで自分の物語らしく編集できるか、考えを温めていたんです。そのため、ものすごい時間がかかりました(笑)。絵の雰囲気が映画のセリフに合ってるかどうか、その場面に合ってるかどうか。取捨選択がすごく大変でした。

──写実主義、印象派、ロマン主義など、分かりやすい名画はもちろん、ジャクソン・ポロックなど現代美術まで時代をまたいで幅広く使っていますが、監督おひとりでこの絵画のチョイスをされたんですか?
シア監督:美大時代の友達の力も借りています。私自身は中国画を中心とした美術を専攻していましたが、友達は油絵専門が多いんですよ。彼らの名前はエンドロールでクレジットさせてもらいました。
──ストーリーのお話を。本作の主題となる親子関係やハン・イエの成長過程は、監督の原体験が反映されてるんでしょうか?
シア監督:私の体験がモチーフになっているところは一部あります。私は思春期のとき、母親と対立していまして。それは映画の中の親子関係よりもひどかったんですよ。でも、修復の過程は映画の中のような努力をしたわけではなく、父が病気になったことで看病などを経て、少しずつ自然に親子関係が修復されていきました。きっかけは自分の経験ではありますが、周りの友人の話も聞いたりして、あの親子の対立構造を考えました。
──息子の視点は監督の経験で補完できるとして、母親の感情は難しかったと思います。息子から拒絶されるわけですから。そこをプロデュースも兼務されたハオ・レイさんとどのように作り上げていったんでしょう?
シア監督:まず、ハオ・レイさんは中国ですごく有名な俳優です。監督からも一般の観客からもすごく人気があり、演技力が抜群です。なので、母親役にはぜひお願いしたいと思ったんですね。初めてお会いした時に、外見も性格もこの役にぴったり合うと確信しました。また母役で一番重要なポイントは、これを演じる俳優さん自身にお子さんがいる方にお願いしたかったこともあり、全ての条件が揃っているハオ・レイさんにお願いしました。お話してみて母性を感じましたし、自分の子どものことを語っているときにはキラキラしている、彼女しかいないと思いましたし、結果、大正解でした。
彼女にはエグゼクティブ・プロデューサーも兼務していただきましたが、キャスティングに関しては彼女も私がやっていいということで、私が行っています。特にハン・イエ役のシア・ハオランですが、もともとプロの役者ではなく、バスケの選手でした。非常にナチュラルで素朴な感じがこの役にぴったりだなと思ってお願いしましたが、今はプロの役者を目指しているんですよ。今回の映画祭上映に来られなかったのは、映画を2本同時進行で撮っていて忙しくなってしまったからなんです。
──才能を見い出しちゃいましたね。
シア監督:シア・ハオランさんの性格的にも、この役にぴったりでした。もちろん、僕が見い出したというのもあるんですけど、彼にはすごい実力がありましたね。演じてくれたハン・イエ役の性格的に彼そっくりだったこともよかったです。心の奥底はすごく純粋で穏やか。善良と言いますか、これがキャスティングするときの唯一の基準でした。この役は、性格は正直で優しい人じゃないとダメっていうのが基準でしたので。
──顔が見えない相手と心を通わせることを表現する映画は数多く作られてきましたし、その媒介は電話が主体でした。今はいろんな手段で顔が見えない人と心を通わせることができるようになりましたが、テレクラをプロットに入れた理由は?
シア監督:今はこういうサービスは殆どなくなり、動画もしくはスマホでの個別のコミュニケーションになりました。でも、本作は2008年の設定ですので、こういうサービスをやっている業者が当時すごく流行っていたことに起因しています。その当時、私自身は高校生だったので、お金がなくてやってませんでしたし、まず社会で携帯がそこまで普及していなかったんですよね。もし、携帯電話を持っていてサービスを利用していたとしても、電話代がすごいことになってたでしょう(笑)。

──日本でもこういうサービスがスマホ以前に流行し、それで破産する人がいました。が、今はもう存在しないサービスです。
シア監督:中国でもそうなんですよ。実はこの映画を撮るときにこういうことを試してみたくて、探し当てたサービスに電話をかけてみたんです。当時はコロナ禍だったんですが、電話に出る人もいませんでした(笑)。それでもどういうものなのか知りたくて、台湾の金馬奨に行く友人に頼んで、台湾に残っているこの手のサービスに電話をしてもらい、リサーチしてもらいました。
──台湾には残っていたんですね。
シア監督:あるにはあったんですが、福建省の方言バキバキのおばあさんが出て、何を喋っているのか分からないような状態だったそうです(笑)。でも役に立ちました。高校生当時、こういったサービスがあることは知っていて興味はあったんですが、通信費が高くて手を出せなかったんですよね。当時、家の近所にそういう電話サービスがあって行ってみたことがあります。携帯電話ではなく、お客とオペレーター双方に電話が用意されていました。入口の電話で何番の人に電話指名できて、その後はふたりで決めるみたいな感じでしたね。
──劇中でも固定電話同士でしたよね。あの異様な雰囲気のオペレーターの部屋。トンネルはロケですか?
シア監督:あそこはペットボトルを生産する工場だったんです。残っているものを全部一回出して、セットを作って撮りました。ペットボトル工場の前は防空壕だったそうです。あの雰囲気を持ったトンネルはあまり残っていないので、3つの街に行って撮りました。
──ロケハンに時間かかりましたね。
シア監督:それほど離れたところではなかったのが幸いでした。テレホンクラブのロケ場所は東京から横浜くらいの距離です。もう一か所はお母さんが働いている工場なんですが、そこがちょっと離れていました。元ペットボトル工場のあのトンネルは防空壕のあと、一時期映画館になってたそうですよ。
──映画館ですか!
シア監督:戦時中の防空壕から映画館になり、そこをペットボトル工場にしてたんですって。あそこは場所的にすごく便利なところにあるんです。しかも、撮影はパンデミックの渦中だったので、通常の状態よりも撮影がしやすかったかもしれません。
──コロナ禍に撮影したのはこの作品にとっては幸運でしたね。
シア監督:そうですね。2019年の終わり頃から撮影を始めたんですが、当時はそこまで規制が厳しくなかったおかげで、多少は人がいた方がいいシーンもちゃんと撮れましたし。ロックダウンが始まってからは編集に取りかかることができました。